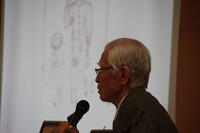学校からのお知らせ
一生懸命が光ります〜掃除の時間〜
昼休みの後、13時20分から13時30分の10分間、掃除の時間になっています。
岩園小学校では一生懸命に取り組むこどもたちの姿を目指して、今年は特に掃除の指導に力を入れてきています。
各掃除場所でやるべきことを明確にするために自分たちで掃除のやり方や役割分担を時間配分とともに考えています。
掃除の時間、子どもたちが掃除に一生懸命に取り組む姿があちこちで見られます。
何かに一生懸命に取り組む姿はとっても素敵です。

1年 図工 ぺったんコロコロ
1年生が、図工の授業で造形遊びを楽しんでいました。
今日の学習は、「ぺったんコロコロ」という単元。
色々な材料でぺったん(スタンプ)したり、コロコロ(ローラー)したりして、形を写して形や色を生み出す楽しさを感じ、積極的に試したり、工夫したりして表すことをねらいとしています。

次々にスタンプして、楽しんでいく子どもたち。
これは楽しそう!
子どもたちは、夢中になって造形遊びに没頭していました。
最後には、みんなで綺麗に教室を掃除しました。
3年総合的な学習「伝えよう!芦屋の魅力!」
3年生が、総合的な学習で「伝えよう!芦屋の魅力!」の学習をします。
総合的な学習はテーマのある単元学習なので、新しい単元に入る時には、学習課題とどんなことをこれから学んでいくのかという大きな流れを先生と子どもたちとで確認していきます。
今日は、単元の導入として、「伝えよう!芦屋の魅力!」というテーマの単元についての概要を先生が説明しました。
3月5日に、宝塚市の山手台小学校の3年生と自分たちとオンライン交流をして、お互いに伝え合うということを子どもたちに伝えました。
そのために、これからの学習をしていくんだということを伝えると、
子どもたちからは、「楽しそう!」の声が上がりました。
子どもたちは、先生の話を聞きながら、どんな学習をどんなふうに進めていくのかイメージを膨らませた上で、先生から提示された5つのテーマから自分が選びたいものを3つ決めました。
それぞれの希望をもとに、グループを決めました。
グループが決まったら、交流会に向けての学習がいよいよ始まります。
交流会は3月5日を予定しています。
4年 福祉体験学習
4年生がゲストティーチャーをお招きして福祉体験学習をしました。

ゲストティーチャーで来てくださったのは、車椅子で生活をされている方です。
車椅子で生活をされている中で、困っていること、工夫されていることについてユーモアを交えながらフレンドリーに分かりやすく話してくださいました。
子どもたちからも質問をたくさんするなど、集中してよく聴くことができました。
体育館ではボランティアのあしや宙の会の方にご協力いただき、車椅子体験をさせてもらいました。
はじめに車椅子の扱い方について、レクチャーを受けてから、友だちとペアを組んで車椅子に乗ったり、押したりしました。
ボランティアの方から、「車椅子に乗っている人に気持ちになって車椅子を押してあげよう。」
とアドバイスがありました。
この体験によって、車椅子に乗っている人にとっては、ほんの少しの段差や傾斜も怖かったり、不便だったりすることが実感できたようです。
子どもたちにとって貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。
4年 ラインサッカー
4年生が体育でラインサッカーの学習に取り組んでいます。
「前!前!」
「こっちやぞ!」
「ラインに戻れ!」
「いけ!」
「パス!」
試合をしている運動場から子どもたちの元気な掛け声が響きます。
そして、得点すると大歓声が上がります。
気温の低い寒い日でしたが、元気いっぱいのプレーでした。
6年 キャリア教育出前授業
6年生を対象にキャリア教育出前授業を実施しました。
講師として、4人の「プロ」をお招きし、プロのパフォーマンスを披露してもらうとともに、キャリアについてのお話を聞かせていただきました。

美容師の方には、ヘアカットパフォーマンスを披露してもらいました。
ヨガインストラクター(パフォーマンスコーチ)の方には、体の動かし方を指導してもらいました。みんなで体を動かして心がリフレッシュしました。
元パラリンピックプロアスリートの方は、ご自身の義足をみんなに見せた上で、競技用の義足に付け替えて、走る姿を見せてくださいました。
和太鼓奏者の方には、和太鼓を演奏していただきました。
プロの皆さんは、6年生に素敵なメッセージをくださいました。
「変わる」ことは、一歩踏み出す勇気が必要。でも「変わる」って楽しい。
自分が決めることが大切。
実際にプロとして働いておられる方たちの話は、子どもたちにも響いたようです。
貴重な体験をありがとうございました。
4年生社会福祉体験
3、4時間目に4年生が福祉体験をしました。アイマスク体験と目の不自由な方の体験談を聞きました。歩き慣れた校舎内もアイマスクがあると全く別の場所のようだと子どもたちが口々に言っていました。お話も普段何気なく通っている道にもある点字ブロックの意味などを教えていただきました。
今日から給食週間です
岩園小学校では今日から7日までの1週間に給食週間を実施します。
全校朝会で、校長先生から給食週間についてのお話がありました。
そして、給食委員会からも給食週間についての詳しいお知らせがありました。
給食の中に入っていると、ラッキーな「ラッキースター」
給食に関するクイズが毎日3問ずつ出される「給食クイズ」
みんなからのリクエストが多いメニューが給食に出される「リクエスト給食」
・・・など給食委員会が中心となって計画しています。
次に、毎日美味しい給食を作ってくれている調理師さんたちに、感謝の気持ちを込めてクラスで作った寄せ書きを渡しました。
どのクラスも工夫を凝らした素敵な寄せ書きです!
子どもたちの給食に対する思いが伝わってきます。
最後に、栄養士の小野先生からは、
「給食室では、皆さんが元気に成長するために栄養バランスを考えた愛情たっぷりの給食を作っています。初めて食べるものや苦手な物でも、まずは一口チャレンジしてくれると嬉しいです。」
とお話がありました。
この給食週間を、毎日当たり前のように食べている給食について改めて見直し、新たな発見をする機会にしてもらえたらと思います。
オープンスクール(高学年)・図工展の最終日
本日は、高学年のオープンスクールを実施しました。
図工展は最終日。




本日もたくさんの保護者の方にご来校いただきました。
ありがとうございました。
オープンスクール(低学年)・図工展
本日は、岩園小学校の低学年オープンスクールを実施しました。
たくさんの保護者の方々にご来校いただき、授業をご参観、また授業に参加していただきました。ありがとうございました。




明日は、高学年のオープンスクールを実施します。
図工展は最終日となります。
お待ちしております。
第90回 図工展 開催
岩園小学校では、図工展を本日から開催してしております。
各学年ごとに個性豊かなたくさんの平面、立体の作品が、体育館に集まりました。






作品には1人ひとりの発想や工夫が溢れ、その子の取り組む様子までが見えてくるようです。
図工展の期間には、子どもたちも学習時間としてたっぷりと鑑賞します。

一つ一つの作品の覗き込んで、その作品の良さや面白さを味わおうとする姿があちこちで見られました。


創造性豊かな作品あふれる図工展をどうぞご鑑賞ください。お待ちしております。
3年アルソック安全教室
毎年、警備会社のALSOKさんが子ども向けの安全教室を2、3年生に実施していただいています。町中で地震が起こった時にどう避難したら良いのか、各班で様々な場所での対応を話し合いながら発表していきます。解説を要所で入れてもらいながら学んでいきました。
1年 昔あそび
1年生が昔あそびを楽しんでいました。
今、生活科の学習で昔遊びをしています。


こま、メンコ、けん玉の中から、好きな遊びを選んで楽しんでいました。
昔遊びをしている子どもたちは、とっても楽しそうで、友だちと一緒にしたり、競争したり、
比べたりするなど、遊びがどんどん広がります。

昔遊びは、遊びを通して、友だちとの関わりが自然と生まれるところが素敵だなと思います。
2年 地獄のリレー
2年生が体育の学習で地獄のリレーをしました。
地獄のリレーとは、自分の番がきたら友だちに追いつかれないように走り抜かなければならないのでドキドキハラハラするリレーです。
後ろの子に追いつかれそうになると、こどもたちの歓声がさらに大きくなり、大いに盛り上がります。
楽しみながらしっかりと運動するので、体も温まり、冬にぴったりのリレーです。



寒い中での体育ですが、子どもたちは元気いっぱいに運動場を走ったり、友だちを応援したりしていました。
笑顔いっぱい ペアタイム
1月24日(金)ペアタイムを行いました。
二十のとびら、じゃんけん列車、大嵐、◯✖️ゲーム、ばくだんゲームなどなど、
それぞれのペア学級で計画していたペア遊びを楽しみました。
どの教室でも高学年がリードして、ペアタイムを進めていました。




3学期になると、これまでの様々な活動を通して、ペア同士の関係も深まってきている様子が伺えます。
子どもたちが楽しく活動するためにルールや役割が必要ですが、異年齢のペア活動を通して、高学年の子どもたちは、自分のリーダーとしての役割を自覚し、低学年の子供たちは、高学年の子どもたちの言動からそのことを学んで行きます。
また、ペア活動の体験を積んでいくことで、高学年の子どもたちは、リーダー的な役割を担うことへの自信を身につけていきます。
こういう活動は学校でしかできない大切にしたいことの一つだと言えます。
今日のペアタイムで、高学年の子どもたちがとても頼もしく見えたことを嬉しく思いました。
縄跳び
子どもたちが、体育で縄跳びを頑張っています。
3年生は、側回旋交差跳びなど少し難しい技にもチャレンジしていました。



・・・「28」「29」「30」・・・とみんなで数えながら、クラスみんなで大縄の八の字跳びにも取り組んでいました。
新しい跳び方ができるようになったり、跳ぶ回数が増えたりすることが、子どもたちの励みにもなります。
2年 図工展に向けて
2年生が、図工展に出品する工作の作品の最終仕上げをしていました。
教室には、それぞれが作った「ともだちハウス」が並びます。
子どもたちは、図工展に出品するために、最後の仕上げに取り組んでいました。
仕上げをしながらも、ともだち同士で作品についての楽しそうな意見交換が始まります。


最後に、自分の作品に題名をつけました。
題名にも子どもたちの個性が表れています。
子どもたちの作品は、1人ひとりの個性が表れていて、その子らしさで溢れています。
今月末の図工展で、子どもたちの作品をぜひご覧ください。
6年 Thank you festival に向けて
6年生が家庭科の学習で、デコレーション部門とクッキング部門に分かれて、Thank you festival に向けての準備を進めています。
卒業を3月に控える6年生が、これまでお世話になった方々へ感謝の気持ちを伝える会として、2月末に行います。


6年生の力を結集して、6年生にとってもゲストにとっても心に残るような素敵な会にして欲しいと思います。
全校1.17集会
1月17日、岩園小学校全校1.17集会を行いました。
岩園小学校では、各学年のカリキュラムに基づいて、災害に対する基本的なことを学ぶ防災学習を実施しています。
同時に、毎年1.17集会を行い、震災の体験談を聞くことを通して、人としての生き方やあり方を考えたり、災害が発生した時にどのように自分の命を守るのかということを知ったり、考えたりしています。

今年は、当時小学校2年生の時に東灘区で被災され、その後神戸市のお寺で住職をされている山中さんにお話を聞かせていただきました。
山中さんは、「普通の小学生の自分が震災で体験したこと」として話してくださいました。
地震発生時、神戸市のご自宅で奇跡的に助かった時の様子、変わり果てた街の様子、学校の避難所での生活のこと、買い物をするために行列に4時間も並んだこと、大阪に避難するのに車で10時間もかかったことなど、被災から4日間のことを小学生の目線で丁寧に話してくださいました。
そして、
4日間だけの避難生活だったが、その時に一番感じたことは、
大変な時に身近な人が助けてくれた温かさ の有り難みと
周りで助け合ってなんとかやっていくことの大切さだった
と話してくださいました。
最後に、
震災を経験して感じたこととして、
毎日を大切に生きること
身近な人となんとか協力してやっていくこと
この2つが大切だと私たちに伝えてくださいました。
子どもたちは、山中さんのお話に真剣な表情で耳を傾けていました。
最後に、全員で「この町が好き」を歌いました。
5年 炊き出し体験
5年生が、防災学習として、炊き出しの体験をしました。
阪神淡路大震災の時には、寒い中の避難生活の中、多くのボランティアのかたが炊き出しで豚汁などの温かいものを振る舞ってくださいました。
防災倉庫に備蓄されている炊き出し用かまどで火を起こし、
炊き出し用の大きな鍋で豚汁を煮込みました。
田植えをしたお米で、ご飯を炊いて、おにぎりも作りました。
5年生は、災害時においての「炊き出し」について学習し、実際に体験してみることで、ノウハウを知るとともに、その役割やありがたみについても感じることができたのではないでしょうか。




6年 SCによる教育プログラム



必要な時に人に相談する力を高めることをねらいとして、本校スクールカウンセラーの先生による教育プログラムを行いました。
「相談するならどんな人がいいか」
話を聞いて気持ちをわかってくれる人
秘密を守ってくれる人
解決しようと動いてくれる人・・・
相談相手に求めたい特徴について、まず1人で考えてから、グループで出し合いました。
この話し合いを通して、
自分は、困っている人が相談したくなる人かな・・・と、自分を振り返る機会にしてもらえたら良いということが子どもたちに伝えられました。
最後に、
SCから「助けられ上手になろう」と子どもたちにメッセージを届けました。
子どもたちの感想には、
「相談を勇気を持ってできるようになると思う。」
「相談をしようと思った。」
「1人で悩まず、人に頼ることも大切だと思いました。」
などの前向きな意見がありました。
必要な時に人に相談する力を少しでも、子どもたちに高めてもらいたいと思います。
6年 校外学習
6年生が、校外学習で、理化学研究所 計算科学研究センターと神戸どうぶつ王国に行きました。
理化学研究所でスーパーコンピュータ富岳を実際に見た子どもたちから、歓声があがりました。
どうぶつ王国では、猿やハシビロコウ、レッサーパンダなどの動物たちとの触れ合いを楽しみました。




2年 昔あそび
2年生が、自分で作った凧をあげていました。
子どもたちは、凧を少しでも高く上げようと、運動場を駆け回っていました。
昔あそびをしているこどもたちは、とっても楽しそうです。



清々しい心で〜書き初め〜
今週は各学年において、「書き初め」を行いました。
1年生は、硬筆で「たこのうた」
2年生は、「たこ上げ」
3年生からは、毛筆で「正月」
4年生は、「明るい心」
5年生は「新しい風」
6年生は、「将来の夢」
と書きました。
一文字ずつ丁寧に書こうと集中している姿は、どの子も輝いています。
そして、心をこめて書いた字は、どれも素晴らしいものです。



池の水が凍ったよ



20分休みに、校庭の池の周りにこどもたちが集まっていました。
池の水に分厚い氷が張っていたからです。
氷を触ろうと子どもたちが手を伸ばしたり、氷を突いたりしていました。
自分の手で氷の感触を確かめながら、氷の分厚さに驚いていました。
冬の寒さを実感する一日でした。
2年 昔の遊び
2年生が、昔の遊びを楽しんでいました。
寒い中であっても、コマまわしや羽子板を子どもたちは楽しんでいました。。



「むずかしいんだよね。」
「かんたんだよ。」
「どうやってするの?』
「あ、これはね‥」
遊びを通して、友だちとの対話が色々と生まれます。
3学期スタート
1月7日(火)岩園小学校の3学期がスタートしました。
4名の転校生を迎えて、806名でスタート。




オンラインでの始業式の後には、
冬休みのことを一言スピーチ発表したり、
転校生を囲んで、自己紹介タイムをしたり、
宿題を確かめながら提出したり、
3学期の当番や係を決めたり、
「冬休みすごろく」をグループで楽しんだり・・・
教室ではそれぞれの学級指導がありました。
休み明けの子どもたちには、笑顔がたくさん見られ、安心しました。
3学期はとても短い学期ですが、次の学年へと繋げる大切な学期です。
どの子にとっても、充実したものになるように気持ちも新たに職員一同取り組んで参ります。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
避難訓練
1月9日(木)地震発生、津波発生を想定した避難訓練を行いました。
火災報知機のベル、非常放送による指示、避難経路確認、避難開始
という流れを確認しました。

校長先生からは、
「避難訓練では、命を守るために2つのことが大切です。
1つ目は、何が起こっているか正しく素早く情報を理解すること。
2つ目は、防災頭巾、足元の注意、おはしもの徹底など、命を守る行動をすること。
地震はいつ起こるかわかりません。いつ起きてもいいように、地震に備えましょう。
お家の人とも話してほしい。」
というお話がありました。
ペア交流遊び
1年生と6年生のペア学級で、交流遊びをしました。
1組、2組、3組、4組ペアそれぞれに、遊びの計画を6年生が立てました。
1組ペアは、火の玉ドッジビーとしっぽ取り
2組ペアは、氷おにとドッジビー
3組ペアは、ドッジボールとリレー
4組ペアは、4人鬼ごっことドッジビー


遊んでいる時の表情は、1年生も6年生も最高に輝いていました。
いつもは司会進行も6年生がしていますが、今回は1年生が司会をしました。


この時期になると、1年生も司会進行を立派にすることができます。
それを6年生が優しく見守っている姿がとても素敵でした。
6年 味覚の授業
12月23日(月)6年生が、高木シェフに「味覚の授業」をしていただきました。高木シェフは、芦屋市で「京料理たか木」というお店を営んでおられます。
高木シェフは、6年生の子どもたち向けて、この「味覚の授業」が、大人になるまでに「味覚」を育てることが大切ということで、フランスで30年以上前に「味覚の1週間」という食育活動として始まったことなどを教えてくださいました。
また、「味覚」には、苦味 塩味 酸味 うま味 甘味の5つがあり、料理する時には、それらのバランスを考えているそうです。
うま味成分には、鰹節のイノシン酸、昆布のグルタミン酸があり、この2つが合わさるとうま味が2倍、3倍になるので、和食の出汁では、必ずこの二つを使うそうです。




子どもたちに、実際に本枯節の鰹節を削って鰹節を作る体験をさせてくださいました。
昆布だしのうまみを感じた後、そこに鰹節を入れて、合わせ出しの味と比べました。
昆布だしに今子どもたちが削った鰹節を加えると、家庭科室いっぱいに出汁のいい香りが立ち込めました。
子どもたちから、「味が変わった。」「あ、こっちの方が美味しい。」という反応がありました。
その後、合わせだしを使った、ごまどうふのお吸い物を振舞っていただきました。
和食の出汁の美味しさを改めて感じることができました。

貴重な体験をさせていただきました。高木シェフありがとうございました。
4年 交通安全教室
4年生が、芦屋市の交通安全指導員の方と芦屋警察の方をゲストティーチャーをお迎えして、交通安全教室を行い、自転車に関する交通ルールや乗り方のマナーを学習しました。
はじめに、自転車のルールを学びました。

次に、踏切の安全な通行の仕方や止まれの標識のある交差点の安全な通行の仕方など、様々な状況での安全な通行の仕方をグループワークで考えました。


その後、交通安全指導員や警察官の方から、正しい方法について教えていただきました。
自分の命を守るための貴重な学習をすることができました。

教えていただいた交通安全指導員の方、警察官の方、ありがとうございました。
5年 外国語スピーチ
5年生が外国語の学習のまとめのスピーチ発表をしていました。


スピーチ内容は、Where do you want to go? の学習で学んだことを活かして、自分がALTのラリー先生に紹介したい都道府県について外国語で紹介するものです。
1人ひとりタブレットで紹介したい内容を提示しながら、自分の紹介したい都道府県について外国語でスピーチしました。
京都、大阪、東京・・・その子らしさの感じられるスピーチ内容とともに、
みんな大きな声で、堂々と話せていたことが、とても印象的でした。
ALTのラリー先生が、一人ひとりのスピーチに対して、評価をかえしてくれます。

子どもたちのスピーチ発表の振り返りには、
「とても緊張した。でもスピーチは楽しかった。3学期は発表をもっとうまくなりたい。」
「英語は苦手だけど、友達のおかげでできるようになりました。」
「3学期は、◯◯さんや△△さんのようにスムーズに言えるようにがんばります。」
などと、前向きな言葉が書かれていました。
みんなの前で発表する経験を通して、友だちの良さを見つけたり、自分の表現に自信を持ったりできるようになっていくのを感じます。
縄跳び
子どもたちは、体育の時間を中心に縄跳びや大縄に取り組んでいます。
2年生の子どもたちも、ずいぶん上達してきました。


大縄をうまく跳ぶにはいくつかのコツがあります。
待つ位置
回っている縄に入るタイミング
跳ぶ位置
抜ける方向
などなど‥
子どもたちは、何度も跳んで行くうちに、それらのコツを体で覚えていきます。
縄跳びは、体力や筋肉がつき、体幹が強くなるというメリットがあります。
全身運動になるので、体全体をバランスよく鍛えることになります。
寒い時期だからこそ、縄跳びで楽しく強い体を作って欲しいものです。
児童会のあいさつ運動
児童会の人の企画であいさつ運動が行われています。
毎朝、代表委員の人たちが、玄関口に立って全校生にあいさつをしています。
あいさつの他にも、楽しくするためにと、じゃんけんやハイタッチ、あっちむいてホイなどのコミュニケーションをする仕掛けも考えて、実行しています。
今日は、その最終日。先生たちもあいさつ運動に加わりました。
あいさつやコミュニケーションをすることで、笑顔が生まれます。




6年 マイセレクト給食
12月12日(木)6年生のマイセレクト給食を実施しました。




家庭科で栄養のバランスの整った食事を考える学習をした6年生が、
給食でも栄養のバランスを考えて、自分でメニューをセレクトしました。
わかめおにぎり、ゆかりおにぎり、ロールパン、クロワッサンの中から2つ
とりの竜田揚げ、鮭のカレームニエル、海老フライ、豚のチーズ焼き、大豆入りハンバーグから2つ、
オレンジ、パイナップル、いちご、から2つ
をそれぞれセレクトします。
カットコーン、型抜きチーズ、キャンディチーズは、自由。栄養バランスの調整に活用します。
牛乳と、オニオンスープと小松菜ソテーは、全員メニューに入っています。
さすがは6年生、たくさんのメニューがあっても、テキパキと上手に配膳していました。
いつもより豪華なメニューの給食にお腹いっぱい大満足で、とっても幸せそうでした。
体育委員会の企画 最終日
12月12日(木)体育委員会の企画で1・2年生の「ふえ鬼」をしました。
3日間続けての実施でしたが、今日が最終日でした。


1回戦が終わると、6年生が鬼になって、もう一度しました。
1・2年生は、みんな張り切っていました。

体育委員会の企画
今日は、3・4年生のケイドロをしました。
体育委員会の人が、運動場に出て、3・4年生に指示をしたり、ビブスの準備をしたり、ラインを引いたりと積極的に動いていました。

45人の警察(おに)が泥棒を追いかけます。
10分間、3・4年生の子どもたちは元気いっぱいに走り回っていました。


体育委員会の人たちは、ルールをみんなが守れるように注意換気をするなど、昨日の反省を生かしつつ、スムーズな運営のために頑張っていました。
最後に、体育委員会の人が、「みんなが楽しそうだったので良かった。」と振り返っていました。
このような達成感を持つことができるのが、委員会活動の良さだと思います。
体育委員会の企画
今週の12月10日(火)からの3日間、20分休みに体育委員会が主催のイベントを行います。
今日は、5・6年生のケイドロです。

体育委員会の人たちが、前に立ってルールなどを説明をします。
警察の人がビブスをきて、泥棒を追いかけます。


20分休みの間の少しの時間ですが、体育委員会のおかげで、思い切り体を動かして、リフレッシュできたようです。
全校平和集会
12月6日(木)全校平和集会を行いました。
岩園小学校では、戦争を二度と起こさないようにという願いを込めて、この平和集会を毎年、続けてきています。
今年度は、低学年と高学年とに分かれて、それぞれ別の方を講師にお招きしてお話を聞きました。
はじめに校長先生から、83年前に日本が戦争を始めたこと、その戦争で、この芦屋市も焼夷弾が落ちて、建物が焼け落ちたこと、たくさんの人が亡くなったことについてのお話がありました。
岩園小学校の校舎も焼夷弾が落ちて、焼け落ちました。その校舎の一部を校長先生が見せてくれました。戦争の傷跡がこんなに近くにあることに子どもたちも驚いていました。
低学年の部では講師の林さゆりさんにお話しいただきました。
林さんは、明治生まれで戦争を体験した方からインタビューをした内容を本にまとめらた方です。
林さんは、戦争の時には、食べ物がなく、安全な場所がなく、学校に行っても勉強もできない、家族と離れ離れになるということを話してくれました。
また、明治時代に3回もの戦争を生き抜いたおじいちゃんの証言についても話してくださいました。
こどもたちは、時折驚きの声をあげながら、真剣に耳を傾けていました。
林さんは、平和を続けるにはどうしたらいいか、自分にできることを考えて欲しいとこどもたちにメッセージをくださいました。

高学年の部では黒田雅夫さんを講師にお招きしてお話をしていただきました。
黒田さんは、現在87才で、7歳の時に開拓団に参加して、中国へ。旧満州で、戦災孤児となり、帰国するまでの体験を絵本「今を生きる 満州からの引き上げの記録」に出版されました。
今日は、息子さんの黒田毅さんと一緒に来てくださいました。
黒田さんは、冒頭で、「戦争は昔の話と思わないでください。
戦争は終わってからも多くの人が亡くなられたり、悲惨な出来事が多く起こったのです。
終わってからのお話を今から話します。」
と話されました。

戦争が終わって、旧満州からどのようにして日本に戻ってきたのかを、絵本の絵を見せながら
話してくださいました。
食べ物がどんどんなくなっていったこと、ようやく収容所に辿り着いたそこでの悲惨な生活。
死体の山、おじいちゃんとの別れ、母親との別れで絶対に生きると強く思ったこと。
キリスト教の修道院の方に助けられ、日本に帰ることができたこと。
辛いお話を私たちに丁寧に話してくださいました。
最後に
命を大切に
家族を大切に
言葉を大切に
今を大切に
人との出会いを・・・繋がりを大切に
というメッセージを私たちにくださいました。
また、黒田毅さんは、
「父親にとってはまだ戦争が終わっていない。
戦争は、みんな傷を負う。
このことを知っておいて欲しい。」
と締めくくられました。
実際に体験された方に話していただけることがこれから難しくなっていく中、
貴重なお話を子どもたちに話していただけたことに感謝しています。
本当にありがとうございました。
4年 ため池作り



4年生が砂場で「ため池」を作っていました。
スコップとシャベルで砂を掘って穴を作り、そこに水を貯めるためにちりとりを埋め込みました。
4年生は社会科で芦屋の水不足を解消するために猿丸安時さんが奥池を作ったことを学習しました。
そこで、ため池を自分たちでも作ってみようということで、ため池作りにチャレンジしました。
子どもたちに「ため池」を実際に作ってみてどうだったかと聞くと、
「楽しかった。けれど、大変だった。」
の声が多く返って来ました。
実際にやってみることで、ため池を作るのに苦労したことがよくわかったようです。
児童会選挙立会演説会



本日、児童会選挙立会演説会を行いました。
4年生の立候補者は8名、5年生の立候補者は12名でした。
この中から、4年生3名、5年生3名、合計6名の児童会役員が選ばれます。
4・5年生が実際に参加し、その他の学年はオンラインで参加しました。
はじめに選挙管理委員会から、岩園小学校の未来がかかっているという観点で選んでくださいと説明がありました。
その後、4年生と5年生の立候補者及び応援者からの演説がありました。
どの立候補者も公約を自分の言葉でみんなに伝えることができました。
最後に4・5・6年生が投票を行いました。


岩園小学校には、岩園小学校のために「自分がやろう。」と、立候補したり、立候補者を支えようと応援者になったりできる人がたくさんいることに対して嬉しく、頼もしく思います。
明日、選挙の結果が発表されます。
当選した人も当選しなかった人も、自分のチャレンジを誇りに思って欲しいです。
6年 出前授業〜みんなで考えるLGB TQ+〜

6年生が宝塚市人権教育指導員の方をゲストティーチャーをお迎えして、ジェンダー平等教育の授業を行いました。
ゲストティーチャーの先生は、レインボーフラッグを持って、教室に入ってこられました。
このレインボーフラッグは、LGBTQ+を象徴する旗として最もメジャーなものであると言われていて、すべての色を含む虹から発想を得て、LGBTQ+だけでなく「全ての人間の多様性を守る」という思いを込めてデザインされています。

先生は、LGBTQ+のそれぞれのことばについての丁寧な説明の後、それらの人々は左利きの人の割合と同じくらいいるということを教えてくれました。
そして、「みんながありのままでいられる社会にするには」という視点で、みんなで考えました。
その中で、LGBTQ+の方に対する差別意識が大きな課題となっていることを知り、こどもたちはそれぞれに自分ならどうしたいかということを考えました。

子どもたちからは、
授業を受けて、色々な性があるということを知りました。それと、みんなにとっての「当たり前」はたまたま人数が多かっただけで全ての人にとっての「当たり前」ではないということがわかりました。このことを色々な人に知ってもらうことが大切だと思います。
心の性と体の性の性別が違う人がいる。このことで差別してはいけないと思いました。
私も深く理解し、寄り添えるようになろうと思いました。
周りの人と少し違うから差別するのはおかしいと思いました。周りの人たちも理解できるように幼稚園ぐらいから学ばせた方が良いと個人的に思いました。
・・・・それぞれにLGBTQ+の問題と向き合い、自分なりの考えを作ることができました。
4年 ものの温度と体積
4年生が理科室で実験をしていました。
黒板には、
「空気は温めると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる。」
と前回の実験のまとめが書いてあります。
今日の問題は、
「水も空気と同じように温度によって体積が変わるのだろうか。」
とあります。
子どもたちは、それぞれに予想を立てて、実験で確かめます。
体積が変わるのか、変わらないのか、予想は分かれます。

実験のやり方をみんなで確かめます。
そして、グループごとに実験し、予想があっているかを確かめました。
そして、水も空気と同じように、あたためると体積が大きくなり、冷やすと体積が小さくなることがわかりました。
自分の予想が合っているかどうかを実験で自分で確かめられるのが、理科の学習の楽しさの一つと言えるでしょう。
5年 家庭科「初めてのミシン」


5年生が家庭科の学習でミシンの実習をしていました。
ミシンを初めて2回目の授業。
ミシンと向き合う子どもたちは、真剣そのものです。
思うようにミシンが動いてくれない時は、「楽しさ」を感じられないようですが・・・。
それでも、
子どもたちにとって、ミシンを使って縫うことは、「楽しい。」ようです。
1年 生活科「葉っぱやみであそぼう」


1年生が生活科の学習をしていました。
「たのしいあきいっぱい」の単元で、はっぱやみであそぼうの学習です。
葉っぱの模様を紙に写す「こすり出し」の技法をやっていました。
また、グループではっぱやどんぐり、松ぼっくりなどを色々にならべて、変身させる遊びもしていました。

こんなふうに1人で自分の思いや願いを実現するべく取り組む場面と、友達と一緒にグループで関わり合い学び合いをする場面を効果的に組み合わせています。
体育
11月も末になり、体育の時にも少し肌寒さを感じる頃となりました。
運動場では、体育の学習をしている子どもたちが寒さに負けずに体を動かしています。

1年生は、的当てゲームをしていました。
グループごとに作戦を立てて、試合に臨んでいます。
的が倒れるたびに、子どもたちの歓声が響きます。
2年生は、長縄をしていました。
8の字とびができるように、縄に入るタイミングや飛ぶ位置などを教えてもらいながら、少しずつ上手にできるようになっています。
これから寒くなってきますが、寒さに負けないで外で体をしっかり動かして、体力をつけていきたいものです。
いじめ防止講演会(コンサート)
11月26日(火)4・5・6年児童を対象としていじめ防止講演会を行いました。
講師として、シンガーソングライター・つっちょさんにきていただきました。
つっちょさんは、いじめは絶対にいけないという思いを歌に込めて、ご自身がいじめられ、それを乗り越えられた体験について、子どもたちに話をしていただきました。
「絵本と音楽を通していじめについて考える機会を少しでも増やせたら・・・。それが私の使命です。」とつっちょさんは、学校講演を精力的に行っておられます。
今日の講演が149回目となるそうです。
講演の後、子どもたちからは、
「いじめはいけないと思いました。今悩みを持っているけど、つっちょの歌を聞いてポジティブに考えようと思いました。」
「いじめがあったとしても、あきらめずに頑張ろうと思いました。」
という感想が出ました。
歌や話を通して、子どもたちの心につっちょさんの思いが届いたのではないかと思います。
つっちょさん、心のこもった歌とメッセージをありがとうございました。
6年 山手中学校見学

11月20日(水)21日(木)6年生が、山手中学校へ見学に行きました。
体育館やグラウンド、芦屋の街を一望できるスポットなどを紹介していただきました。
図書館は、小学校とな違うジャンルの本があったり、新刊があったりととても魅力的でした。
今日は、中学校の図書館で1人一冊借りることができました。
この本を活用して、ブックトークをする予定です。
山手中学校の図書員さんからのメッセージ
ありがとうございました。
1年 秋見つけ
1年生が、生活科の学習で岩園天神社、岩ケ平公園、八十塚古墳に秋を見つけに出かけました。
それぞれの場所のたくさんの秋を見つけました。どんぐりもいっぱい拾いました。
天候に恵まれ、気持ちよく活動できました。
参観音楽発表会
本日音楽発表会がありました。音楽の時間に練習した合唱、合奏、リコーダー奏等を各学年ごとに発表し、保護者や地域の方に参観いただきました。大きな混乱もなく、子供達も日頃の練習の成果を存分に発揮することができました。お子様の学年以外の取り組みも後日DVD(販売)で見ていただくことができますので、興味がある方は購入ください。
尚、当日の音楽発表会の運営にあたりまして、PTA執行部の方々にはお力添えをいただきました。心より感謝申し上げます。
今後も本校の教育活動に対してご理解・ご協力をお願いします。